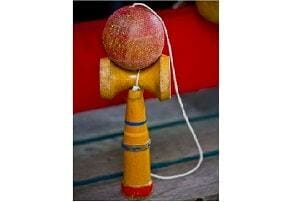こんにちはTORAです。
5年前くらいでしょうか、けん玉=KENDAMAとして世界的に流行りました。
私も子供のころはよくやってました。
以前テレビで観ましたが、柔道の練習にけん玉を取り入れたりしてました。
けん玉は膝のクッションを使ってやるので、良い練習になるらしいです。
今回はそんな「けん玉」についてお伝えします。
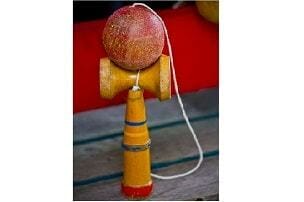
日本のけん玉(拳玉、剣玉、ケンダマ)
けん玉は日本で生まれたかのように思われがちですが、実はそうではありません。
日本にはシルクロードを通り中国に入り、江戸時代に中国人によって長崎に伝えられたという説です。
文献からは、1777年に長崎に伝わったと記載されているらしいですよ。
ただ、日本でけん玉が広まったのは大正時代で、現代のような大きな玉とやや大きさが異なる
二つの皿(支柱の裏も加えれば3皿)となり、駄菓子屋で売られるようになってからと言われています。
けん玉の歴史
けん玉の起源についてはいろいろな説があるそうです。
16世紀のフランスで生まれたという記録があります。
そのほか、ギリシャや中国という説もあって、現在はまだ確認されていないようです。
古い記録では、16世紀のフランスで国王アンリ3世のころです。
ピエール・ド・エストワールが「1585年の夏、街角で子どもたちがよく遊んでいる
『ビル・ボケ(Bilboquet)』を、王様たちも遊ぶようになった」と書いています。
貴族や上流家庭のビル・ボケは象牙などを使い、彫刻がほどこされていたのでとても高価なものでした。
現在世界各地にあるけん玉の多くはこのビル・ボケが伝わったものと考えられます。
けん玉の魅力
昔ながらの遊びとして親しまれている「けん玉」
性別や年齢に関係なく遊ぶことができるものの一つです。
「けん玉」には色んな技があります。
現在では単なる遊びの「おもちゃ」ではなく、スポーツ競技としても人気を集めています。
「公益社団法人日本けん玉協会」という団体もあり、全国でその技を競う大会も数多く開かれています。
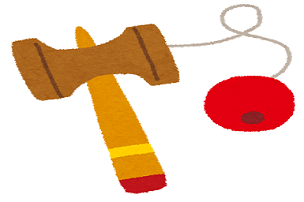
けん玉の技
-
-
- 大皿、中皿、小皿
下げた玉をまっすぐ引き上げて、お皿に乗せる基本的な技です。
-
-
- 乗せる場所によって大皿、中皿、小皿に分けられます。
-
-
- とめけん
まっすぐに下げた玉を引き上げ、けん先で受ける技です。
-
-
- とても難しいです。
-
-
- 飛行機
玉のほうを持って、そのままケンを静かに前に振り出し、
-
-
- 逆さまに落ちてきたケンを玉で受ける技です。
-
- 激ムズです。
-
-
- 世界一周
ケンの部分を持って、玉を真上に引き上げ、小皿、大皿、最後にケン先で玉を受ける連続技です。
-
-
- これが出来たらあなたもけん玉マスターです。
まとめ
どうでしたか?これであなたもけん玉に対する知識が一段と深まりましたね?
是非とも機会があれば健康の為、気分転換などに、けん玉をあの頃のように楽しんでみてください。
今日も一日お疲れ様でした。